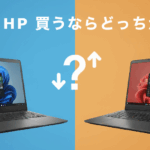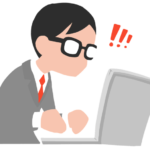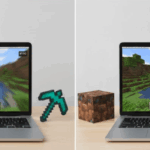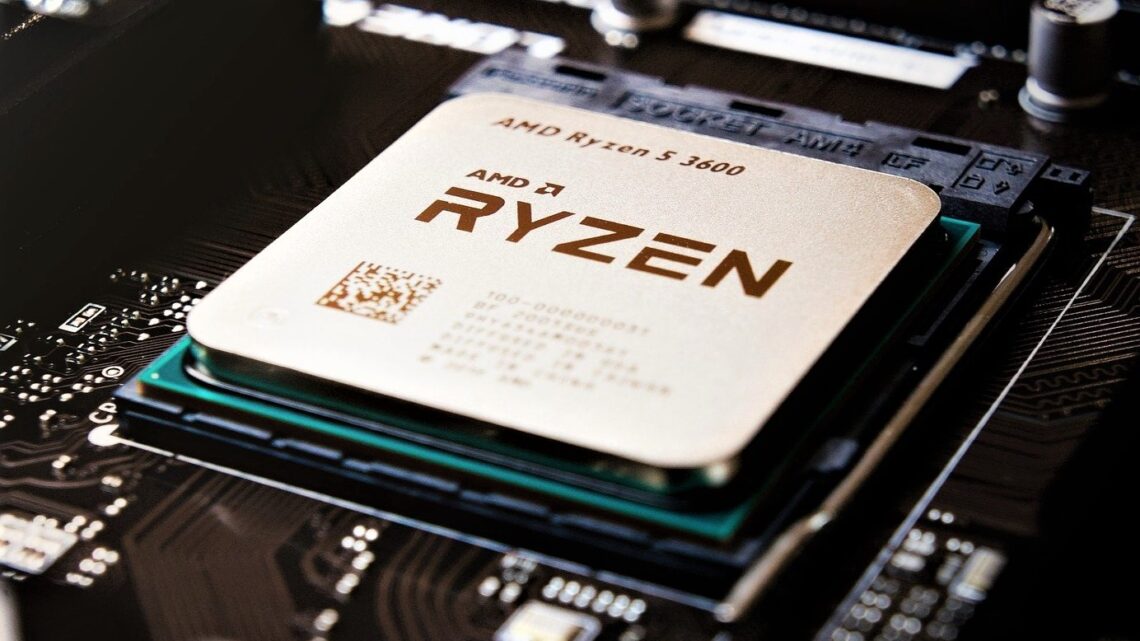
内蔵GPUはIntelかAMDどっちが良い?もはや優秀過ぎてグラボいらない説【Intel Arc vs Ryzen Radeon】

この記事を書いている人(せせら)
普段はITフリーランスとして活動しています。
個人で作業効率化サービスを運営し、挑戦を続ける人々を静かに応援しています。
目次
最近の内臓GPUが優秀すぎる!
最近の内臓グラフィックスの性能が大幅に向上しています。IntelではArc、AMDではRadeonシリーズが代表的ですね。
実際にどの程度内臓GPUの性能が向上しているのかは、下記の表を参考にしてみてください。
主要な内蔵グラフィックス性能一覧
| シリーズ | モデル | 内蔵GPU | コア数 | クロック数 | 理論性能 | 同等GPU |
| 3000 | Ryzen 5 3400G | Vega 11 | 11 | 1400MHz | 1.9 TFLOPS | GT 1030 |
| 3000 | Ryzen 3 3200G | Vega 8 | 8 | 1250MHz | 1.4 TFLOPS | GT 1030未満 |
| 4000 | Ryzen 7 4800U | Vega 8 | 8 | 1750MHz | 1.8 TFLOPS | GT 1030+ |
| 4000 | Ryzen 5 4600U | Vega 6 | 6 | 1500MHz | 1.2 TFLOPS | GT 1030 |
| 5000 | Ryzen 7 5700G | Vega 8 | 8 | 2000MHz | 2.0 TFLOPS | GTX 1050 |
| 5000 | Ryzen 5 5600G | Vega 7 | 7 | 1900MHz | 1.8 TFLOPS | GTX 1050- |
| 6000 | Ryzen 5 6600U | 660M | 6 | 1900MHz | 1.9 TFLOPS | GTX 1050 |
| 6000 | Ryzen 7 6800U | 680M | 12 | 2200MHz | 3.6 TFLOPS | GTX 1050 Ti |
| 7000 | Ryzen 3 7440U | 740M | 4 | 2500MHz | 2.7 TFLOPS | GTX 1050 |
| 7000 | Ryzen 5 7640U | 760M | 8 | 2600MHz | 5.6 TFLOPS | GTX 1050 Ti+ |
| 7000 | Ryzen 7 7840U | 780M | 12 | 2700MHz | 8.6 TFLOPS | GTX 1650 |
Intelの情報がなくてすみません。
この表を見てみると、最近の内臓GPUはローからミドルクラスのグラボと同じくらい高性能である事が分かると思います。
もはや、一般ユーザーにとってはこのくらいで十分ですよね!
なぜ内臓GPU(iGPU)の性能向上を目指しているの?
AMDもIntelも、比較的最近に内臓GPUの性能向上に力を注ぎ始めました。
でも、なぜ内臓GPUの性能向上をしたいのでしょうか?
その理由は、AMDが公表している「APU戦略」に答えが乗っています。APU戦略の内容を要約すると以下のような感じです。
- 高価な専用グラフィックボードは、実はユーザーの一部しか買わない
- 大多数のユーザーは内蔵グラフィックスで十分な性能があれば、それで満足
- だったら、内蔵グラフィックスの性能を上げて、この「普通のユーザー」市場を押さえたい
これが狙いです。実際、Steam(PCゲームの配信プラットフォーム)の統計を見ても、ユーザーの多くは中位~低位のグラフィックス性能で十分なゲームをプレイしています。
インテルも同じ考えで、Arc(アーク)という独自グラフィックスを開発し、内蔵GPUの性能向上に力を入れています。
つまり両社とも、「ハイエンドよりも、一般ユーザーが満足できる性能の内蔵グラフィックス」という市場を重視しているんですね。これは企業としても、開発コストを抑えつつ大きな市場を獲得できる賢い戦略だと言えます。
IntelとAMDの内臓GPUってどっちが優秀なの?
IntelとAMD、現状どちらの内臓GPUの方が優秀か気になりませんか?
両者ともかなり性能向上はしているのですが、2024年の時点だと圧倒的にAMDが有利です。
AMDが内臓GPUに強い理由:
- Radeonグラフィックスの長年の技術蓄積がある
- 長年APU(CPU+GPU)開発に注力してきた実績がある
AMDは内臓GPU開発の歴史があるのよ
AMDはCPU+GPUの統合型プロセッサー(APU)分野で、実は長い歴史があり、2011年に初めてAPUを発売して以来、この分野をずっと重視してきました。
なぜAPU開発に注力したかというと、
- 当時はIntelと比べて資金不足だったので、APUで市場を押さえる戦略をとった
- PS4やXbox Oneなどのゲーム機にAMDのAPUが搭載され、開発ノウハウを得れた
この二つです。
AMDは資金がない中、工夫してた
元々、「高性能CPU市場はIntel」「高性能GPU市場はNVIDIA」が強かったんですよね。
AMDも頑張ろうとはしたのですが、やはり高性能なCPUやGPUを開発するのは資金が必要なので、当時としては資金力が乏しかったAMDは苦境に立たされていた訳です。
そこで思いついたのが「そこそこの性能のCPU + そこそこの性能のGPU」という手薄な中間市場にアプローチをする方法です。
- そこそこの性能のCPU開発なら開発資金を抑えられる
- そこそこの性能のGPU開発なら開発資金を抑えられる
- CPUもGPUも開発資金を押さえられているので、手頃な価格で提供できる
- 一般ユーザーは、そこそこのスペックの物が手頃な価格で手に入ればいい
- 実は、その一般ユーザーの占める市場がかなりデカかった
このような感じで、「限られた資金」「効率的な開発」「大きな市場」を実現したわけです。
さすがAMDですね。
PS4などのゲーム機にAMDが採用された理由も、この「そこそこの性能」「手頃な価格」が決め手となった形です。
そんな訳で内蔵GPUはコスパが良い
これまでの説明にあるように、「手頃価格」「そこそこの性能」を実現しているのがAMDのCPUと内臓GPUなので、コスパにかなり優れています。
具体的にどんな感じかというと、5万円前後のミニPCでAPEX、VALOLANT、COD、BF、モンハン、原神、等の高負荷な3Dゲームを楽しむ事が可能です。
以前書いた私の記事に、大体5万円前後でPCゲームがプレイできるコスパ最強のPCをまとめたので、購入を検討していたらぜひ見てみてください。
まとめ
内臓GPUの成長が早すぎて、ローからミドルクラスのGPUに関しては存在意義が薄れてきましたね。
3Dゲームを軽く楽しむ程度や、動画編集、画像処理まで、別途GPUを買わなくても済んでしまいます。これはもはや、一般ユーザーはグラボなしでも十分と言えるのではないでしょうか。
実際に、内臓GPUで3Dゲームがどこまで楽しめるのか検証した記事もあるので、よかったら見てみてください。
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。